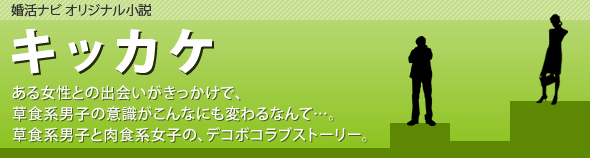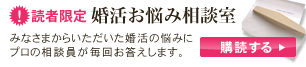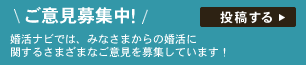「こんばんは。ここ、いいですか?」
「は、はい。どうぞ。」
こんなにきれいな人から「いいですか?」なんて聞かれて断るやつなんかきっといないだろう。
突然現れた彼女がコートを脱ぎながら、このぶりっこ女性と話している間、僕の胸の鼓動はどんどん早くなるばかり。
いくら暖房が効いた室内とはいえ、こんな寒い日にうっすら汗をかくくらい体が熱くなっていた。
これを一目ぼれというのだろうか。
ビビビと電流が走った気がした...というのは、気のせいではなく、どうやら本当に「運命」に出会ったのかもしれない。
僕はそう確信した...はずだった。
二次会というこの宴も、すっかりあちこちで打ち解けた輪ができて、新郎新婦も向こうの輪で盛り上がっている。
僕とこのぶりっこ女性と、そしてこのスレンダーな女性の三人で、「じゃあ、改めて乾杯!」と乾杯をしなおした。
「この子はね、理子っていうの。ちょっと用事があってさっきまで抜けてたんだ。」
そう言って、この女性の情報をくれるぶりっこ女性が僕には救世主に見えた。
さっきまで苦手だと思っていたのに...。
というか、ようやくこのぶりっこ女性の発言を初めて真剣に聞いたような気がする。
「どうも。元木と言います。」
ああ。こんな時に、気の効いた一言が言えない自分に腹が立つ。
「改めまして。佐伯と言います。」
彼女が微笑んだ。
その微笑に、僕はゴッソリとハートを持っていかれてノックオン。
佐伯理子...かぁ。にこっと笑う顔が、スレンダーで知的に見える。
外観と違ってとてもかわいらしいので、僕の瞳は彼女に釘付けになっていた。
「元木さんってねぇ、嵐山銀行に勤めてるんだって!」
「えーっ?ほんとですか?私よく行くんですよ!」
「え? 本当ですか?」
「どこの支店にいるんですか?」
「僕は、駅前にある支店です。」
「あー残念!駅前のトコはたまーに行きます。私がよく行くのは、アーケードの中にあるところかな。」
「家か会社が近い...とか?」
「はい。アーケードにある薬局で事務してるので。」
なるほど。新婦の同僚関係か...。
「でも今度から銀行に行くときは、駅前に行くようにしますね!」
おいおい。さっきから聞いてれば...「残念!」だとか「次から駅前支店に行く」だとか、思わせぶりな態度。
「案外、軽い感じの女性なのか?」って頭をよぎった。
もしかしたら、その辺の女性たちと同じかなって。
よくいるだろう?
思わせぶりな態度が得意な女性って...。
僕はそういう女性によく騙されたクチだから、その点の防衛反応はよく働くんだ。
僕の体の防衛ランプがピコンっと反応している。
可愛い。確かに可愛い。
でも、「本気」になったらマズイような気がする...。
前の彼女と別れてからも、女性と会う機会はあった。
でも、この防衛ランプが少しでも反応したら、僕はそれ以上に進む気になれずにいた。
だから、今でも独り身なんだけど...。
でも待てよ。
じゃあ、さっき感じた『ビビビ』は何だったんだ?
僕の勘が鈍っただけなのか...?
...なんて、一人で考え込んでいたとき
「新郎のお友達なんですか?」
という彼女の声で我に返った。
「あっはい。尚也とは高校の同級生で。」
「そうなんですね!優しそうな旦那さんですよねぇ。」
「はい。男から見ても、とってもいい奴ですよ。」
「いいなぁ。2人すごく幸せそうですよねぇ。」
うっとりしながら、向こうの新郎新婦を見る彼女の目は、すっかり乙女モードになっている。
「予定とかないんですか?」
「えっ?」
お酒のせいなのか、僕は突然に彼女にこんな質問を投げかけていた。
「結婚の予定とか...。」
「いや。ぜんっぜん。予定があったらいいんですけどねぇ。」
少し困ったように彼女が笑う。
ということは...、恋人はいないのだろう。
僕が思わずこんな質問をしたのには理由がある。
それは、彼女の右手薬指に指輪が光っていたから。
指輪をしていたのが左手だったというわけでもないし、それがエンゲージリングでもなく、何の根拠もない けれど、ただ、なんとなくだけど、それを見た時に彼氏がいるのかなと思ってしまったから。
でもその予想は単なる思い違いだったようだ。
「よかった」...そう少し安心している自分の気持ちが、不思議に思えた。
「この子ねぇ。彼氏いないんですよ。合コンとかでいっぱい紹介してるんですけどねぇ。」
「ちょっと、余計なこと言わなくていいじゃない!」
「だってほんとじゃぁん。元木さん、誰かいい人いたら紹介してくださいね。」
「はっ はい。」
いきなりの展開だから、慌ててしまった。
でも、正直、彼女には誰も紹介したくない。
それでもそんな気持ちを読み取られないように、僕は微笑んだ。
「ほら、よかったねぇ。理子。」
「はは。じゃあお願いしまーす。」
「あ、いいですよ。紹介できる相手がいましたら、ぜひ...」
「ほんとですよ!!じゃあ、今度合コンでも設定してくださいね。」
外見的には知的で物静かな感じだけど、理子さんはノリもよく結構積極的だった。
見かけとのギャップに、僕はちょっと戸惑ってしまう。
でも、それも嫌な感じはしなかった。
「じゃあさ、連絡先教えて下さいよぉ。」
ぶりっこ女性が携帯を取りだした。赤外線通信で、番号交換。
「理子も交換したら?」
ぶりっこさんに促された彼女は、少し遠慮がちな表情を見せた。
「えっ。私も教えてもらっていいんですか?」
さっきまであんなに積極的な発言していた子が...、急に何を言いだすんだろう。
ますます女ってわからない。
「もちろん。」
2人の携帯を合わせて通信しながら、携帯を持つ手が少し震えていた僕。
心の中で防衛ランプが警報を鳴らしているけれど、もうそんなのおかまいなしになっていた。
元木拓朗 銀行マン。
彼女と別れて3年目の冬に、僕は久しぶりに恋をした。
理子さんと番号交換したすぐ後に、三次会へと移ることになった。
でも、僕は翌日の出勤が早いこともあって、二次会がお開きになった時点で家路についた。
健も含めて三次会に行く連中も結構いた。
そしてそのメンバーに理子さんもいたのだ。
三次会の誘いに彼女ははりきって参加しにいったっけ。
そりゃあ、三次会に参加する・しないは本人の自由だし、僕がとやかくいうことじゃない。
...でも、あの後、彼女がどうなったのかがすごく気になって仕方がなかった。
家に帰ってからも考えるのは彼女のことだけ。
今頃どんなやつらと飲んでいるんだろうかなんて考えていたら、なかなか眠れない。
「三次会行けばよかったかな...。」
なんて後悔しても、今や遅し。
やっぱりあの「ビビビ」は勘違いではなく本物だったんだと実感しながら、僕は願った。
健が理子さんにアタックしていないことを...。
健が相手では太刀打ちすることは無理だろう。
アイツはいい男だし、女性の扱いにもなれている。
女性にはとびっきりの紳士である健に、もしかしたら、理子さんが惚れているかもしれない。
「相変わらず、情けない」
そう呟いてから、僕は深いため息を吐いた。
理子さんとはもう会うこともできないかもしれない。
連絡先を交換したからといって、僕から連絡を取ることがなかったら、きっとこの出会いもこのまま終わってしまうのだろう。
僕は、電話をかけることもメールを打つこともできないまま、ただ携帯を握りしめるだけだった。