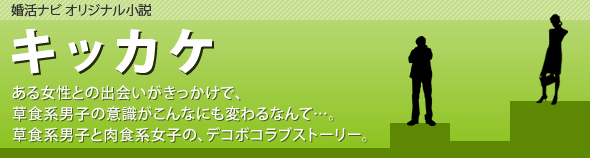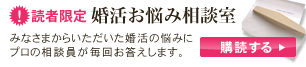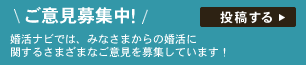不意打ちという言葉は、こういう時に使うものだろう。
理子さんからの連絡が携帯に来るだろうと思っていた僕は、まさか彼女が後ろに立っているとは思いもしなかった。
「ごめんなさい。だいぶ待ったんじゃないですか?」
「いえ。さっき来たとこです。」
って...、だいぶ待ちました!なんて言えないよな。
「ねえ。どこに行きます?」
あの結婚式二次会の出逢い以来、今日の昼に再会しただけというのに、ランチに誘われるは、こうして夜に会う約束も取り付けるわと、完全に理子さんのペースにはまっている。
本当は僕が格好良く誘うべきだったのに...。
どこに行くかと聞かれた僕は、ようやく自分のペースで理子さんを案内することとなった。
とはいえ......
こんな時に女性はどこに行きたいものなのか?
なんせ3年もデートすらしたことなかった身分なので、思ってもみなかった突然のシチュエーションにとまどう。
お茶?
いやいや。
お互い、今食事を済ませたとこだ。
飲みに行く?
いやいやいや。
しょっぱなから、飲みとはいかがなものか...。
短時間だったけどいろいろなことが頭をよぎった結果、僕が言った言葉。
「ゲームセンターとかどうですか?」
そう言ったものの、僕の心には"やってしまった感"があった。
よりによって、ゲームセンターって...。
僕自身そんなにしょっちゅう行く場所でもないのに。
僕は世間的には「草食男子」かもしれないけど、別にゲーマーでもなく、おたくでもない。
でもゲームセンターに誘われた女性にはそう映ってしまうかもしれない。
しかし、後悔した僕の心とは裏腹に
「あっ。いいですねっ。行きましょう!!」
と言ってくれた。
(これでよかった?)
半信半疑ではあったものの、少し歩いたところのゲームセンターに行くことになった。
「わー。ゲームセンターなんて久しぶり~。」
「僕もです。あまり来ないもので。」
何気なくゲーマーじゃないことを主張。
「私ゲームって下手なんです。あっ、こんなのだったら、何度かしたことがありますよ。」
そう言って理子さんが指差すのは、レーシングゲーム。
よくあるカートゲームだ。
「してみます?」
「うんっ。対戦しましょうよ。」
時に見せる子供のようなとっても無邪気な笑顔に、僕も心が弾んだ。
「負けませんからね。」
そう意気込んだ理子さん。
きゃーきゃーとハンドルを切るたびに歓声を上げながらゲームをする彼女の隣で、僕はなんとしてでも理子さんと付き合いたいという思いを再確認した。
「えー。私ビリだって...。」
ゲームを終えた彼女が、本気で落ち込む姿も可愛らしい。
そういう僕も、大人げなくゲームに本気になって、彼女にわざと負けることなんて頭になかったけど...。
ふと、女子高生たちがプリクラを切り分けている姿が目に入った。
「元木さん、知ってます?最近のプリクラってものすごく高性能なんですよ。」
「へー。」
僕は、この時に気づいた。
ゲームセンターという場所は、なんといっても音がうるさい。
となると、このゲームセンター内で話す時には、自然と顔が近づいてしまうということを。
つまり僕たちは、会話を交わすたびに顔を近づけて話しているというわけだ。
ゲームセンターを選んでよかった、なんて今更ながら思った。
「美白モードは当たり前だし、びっくりするくらい写りがいいんですから!」
彼女はまだ、プリクラについて熱く語っている。
「ほー。じゃあ、撮ってみる?」
よく言った!僕にしてはかなり積極的な行動。
そう。
今までの僕みたいに奥手なままでは、きっと理子さんは手に入らない。
この恋を逃がすまいという本能が、今の僕の行動を操っているかのようだった。
「えっ!?」
えっ!?って、いきなりプリクラ撮ろうって言ったら、女性から引かれるものなのか?
ひきつったと思われる僕の表情は、理子さんの言葉のおかげで一瞬だけのものとなった。
「えっ!?......一緒に撮ってくれるんですか?」
「せっかくだから撮りましょうよ。」
「やったー。」
こないだの番号交換の時といえ、理子さんはかなり積極的なようで、遠慮がちな面も持ち合わせている。
ちょっと謎めいているけれど、実はそんな謎めいた部分も魅かれる理由の一つだ。
慣れた手つきでプリクラの機械を操作する姿を、僕は何もせずに、いや何もできずに待っているだけ。
そして仕上がった写真に書いてあった言葉。
『初デート記念!』
僕はこの言葉が心から嬉しかった。
どうしてもモノにしたいこの恋。
うまくいくかもしれない、と期待するのはまだ早いのだろうか。
「元木さんも持っていて下さいね。」
さっきの女子高生がそうしていたように、理子さんが切り離して渡してくれたプリクラの半分を僕に渡した。
出逢いからちょうど1週間経った日曜日。
僕は、彼女との待ち合わせ場所で理子さんが来るのを待っていた。
実は、誘ったのは、初デートとも言えるプリクラデートの晩のことだった。
いつになく積極的だった僕は、家に着いてからもまた、彼女の声が聞きたくなって電話をかけたのだった。
「もしもし。遅くにごめんね。寝てなかった?」
珍しい。実に珍しい。
僕から、女性に電話をかけるだなんて。
今までの自分としてはありえないような行動だったが、これが恋愛マジックというものなのだろう。
「いいえ。寝てなかったですよ。」
「今日はせっかくランチに誘ってくれたのに、ごめん。」
「いいんです。急だったから。それに、夜会えたから嬉しかったです。私ね、早速プリクラ手帳に貼っちゃいましたよ。」
彼女のストレートな発言にドキッとして、言葉がつまりそうになる。
...なんて、情けないことを言っている場合じゃない。
「今度は僕から誘わせてもらってもいいかな。週末とか予定ある?」
「週末ですか?土曜日は仕事なんですけど...。日曜日でよかったら...。」
「じゃあ、日曜日にどこか遊びに行こうよ。」
「はい。」
こうして僕は、初めての出逢いから一週間後に、理子さんと二度目のデートを実現したのだった。