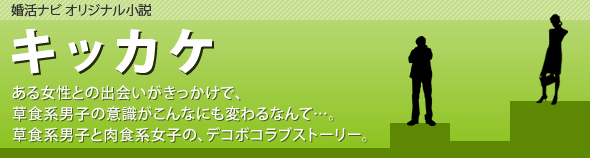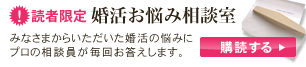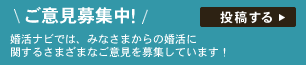「理子ちゃん。知り合って間もないけど、こんな僕と付き合ってくれる?」
僕はこのセリフを言うために、今日のデートをセッティングした。
毎日会っていて、手をつないで歩く僕たちをはたから見れば、きっと「付き合っている2人」に見えるだろう。
最近では、決定打がないままにいつの間にか『付き合っている』というカップルが多いのも確か。
でも僕は、こういうことはきっちりとさせたかった。
それに、女の子ってこういうことにはきっとこだわるんだろうと思っている。
男の中では、『そんなことにこだわるなよ...』なんていうやつもいるけれど、これは2人にとってとても大切なことだと思う。
あやふやなまま接してはいけないと思っているし、自分の気持ちをきっちりと伝えなくてはならない。
これは、僕が女の子に対する気持ちで、昔から変わらない。
実はこんな性格の僕を『女々しい』なんていう女の子もいて、そんな時は自分を変えようかとも思ったこともあるけれど、それじゃあ本当の僕じゃないということも気づいた。
この僕の真剣な気持ちを、きっちりと理子ちゃんに伝えたかったから......。
てっぺんを超えた観覧車の中の僕たちは、しばらく黙りこんだままだったけど、理子ちゃんの一声で明るいものになった。
「よかった。ジェットコースターで気分悪くなっちゃったのかと思ってたから。」
どうやら緊張していた僕は、いつの間にか口数が少なくなっていたらしい。
「そんなことないよ。今日言おう!って思ってたから......、緊張してたのかな?」
「それなら、よかった!」
そう言って無邪気な笑顔の理子ちゃんが、急に立ち上がって向かい側の席に座った。
ゴンドラが揺れる。
絶叫系が苦手な僕は、ゴンドラの揺れも苦手なわけで...、勘弁してくれよ...。
「へへー。ちょっと意地悪しちゃった。」
「さっき、怖いからこっちに座るって言ってたんじゃん。」
僕はそう言うと、再び理子ちゃんの隣へと移った。
そしてまた軽く唇にキス...。
僕たちは、晴れてカップルとなった。
「ねえ。いつから私の事気になってた?」
夕食を食べている時に突然こんなこと言いだすもんだから、食べていたものがのどに詰まりそうだった。
「えっ?いつからって?」
そりゃあね...いつからって...。
「理子ちゃんは?」
照れから思わず聞き返してしまった僕。
「私はねぇ、初めて会った時にこの人いい感じの人だなって思ったの。」
「マジで?」
僕は意外だった。
「ほんとだよ。拓朗君は?」
「実は...僕も。初めて会った時に一目ぼれというか...。」
だんだんと声が小さくなってしまったけど、ここは男らしくひとつ。
「ちょっと古いかもしれないけど、"ビビビ"ときたんだよね。」
言ってる僕も恥ずかしかったけど、理子ちゃんは顔を赤らめて目をまんまるくしている。
「そんなに...驚いた?」
「うん...。だって拓朗君さ、三次会来なかったじゃない。その時にね、"あ~この人は私の事を何にも気に留めてないんだな"って思ったの。」
「うそっ。僕の方こそ、理子ちゃん嬉しそうに三次会に行ったし"僕は気にされてないな"って思いながら、三次会行けば良かったって後悔したんだから。」
お互いの想いが同じだったということで、もう僕たちは笑うしかない。
そして気持ちというものは言葉にして伝えなければいけないというものを痛感した。
あの時は、翌日に理子ちゃんが銀行に来てくれたからよかったけど...、もし理子ちゃんが押しの弱い子で...、銀行に来ることもなく"自分は気にされていない"と思ったまま時が過ぎていたら...。
もしかしたら、今の2人はなかったかもしれない。
もしかしたら...。
そう思ったら、理子ちゃんが積極的な子でよかったと思った。
僕自身、彼女に"ビビビ"ときたのは事実だけど、彼女の押しやこの独特のペースを知らないままだったら、本当に恋愛に発展しなかったのかと思うと、ぞっとしながら夕食を口にしていた。
いつものように理子ちゃんを駅まで送るつもりだった。
今日はずっと一緒にいたし、今日の目標も無事に果たせた。
でもどうも、理子ちゃんの様子がおかしい。
というかいつものように機嫌が悪くなった。
「どうした?」
僕はとぼけて聞いてみた。
理子ちゃんは黙っている。
「どうしたの?」
まだ、黙ってる。
「どおしたの?ったら!!」
僕は彼女のわき腹をくすぐって、ふくれっ面を笑顔にと変えさせた。
「だって...。」
わかっている。
彼女は帰りたくないのだ。
帰る時にはいつもそうだから。
そんな風に思ってくれるなんて、とても嬉しいけど...、実家住まいだしね...。
「帰りたくないの?」
彼女がうなずく。
「でもお父さんとお母さん心配するよ。」
「大丈夫。」
「大丈夫じゃないでしょ...。」
「言ってきたから...。」
「えっ?」
「今日はね、友達と遊びに行くって言ってきて...、そして友達の家に泊まるって言ってきた...。」
......ということは、理子ちゃんは今日お泊り覚悟で来ていたと...。
まさか...の展開だ。
やっぱり理子ちゃんは積極的な女の子...だよな。
「ダメ?」
そんな上目づかいで見られたら...ダメとも言えない。
というか、ダメという理由もないわけだけど...。
「ダメ...じゃないけど、びっくりした。」
つい本音を言ってしまうのが僕の長所なのか短所なのか...。
「へへっ。」
いたずらっぽく笑う彼女の手を取り、僕は自宅へと向かった。