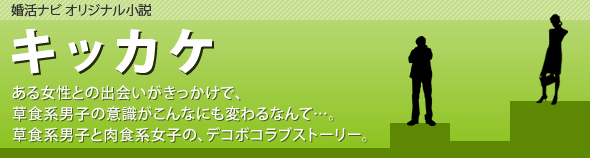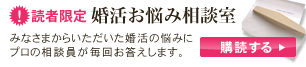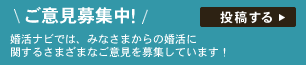僕と理子ちゃんの間に、予想もしないような別れの訪れ。
彼女からの
『もう私たちダメだと思う......』
というメールを受け取ってから、僕はしばらく考えた。
その後、何度か電話やメールを送ったけれど、彼女からの反応はない。
本当は別れたくなかった。
しかし、今の僕と一緒にいても理子ちゃんは辛いだけかもと思った僕は、それ以来、連絡をすることを断った。
散々な終わり方...。
それ以来、僕は無理やりサッカーに明け暮れ、理子ちゃんとのことを考えないようにしていた。
でも、それは長くは続かなくて...。
ようやく、自分の気持ちを伝えるべく行動を起こしたのだった。
新しい年が明けて、理子ちゃんとの出逢いからちょうど一年経ったころ、僕は彼女に手紙を書いた。
年末から進めていた、この"計画"を実行するために......。
理子ちゃん
お久しぶり。元気にしてますか?
この数カ月、理子ちゃんのことを考えないようにしていたけど、考えないようにすればするほど、駄目でした。
前にメールを送ったように、確かに僕は理子ちゃんに嘘をついた。
元彼女との再会は、理子ちゃんが思っているようなことは決してなくて、メールに書いたことがすべて。
でもそれを知っても、返事がなかったということが理子ちゃんの返事なんだと思う。
でももう一度だけ、僕の気持ちを聞いてほしいので、待ってます。
2月14日に、ディズニーシーのエントランスで。
僕が年末から立てていた"計画"。
ディズニーシーでは、"バレンタイン・ナイト"という期間限定のイベントがある。
入手困難なこの数量限定チケットを僕は必死で手に入れた。
バレンタインデーは、女の子が愛を伝えるイベントだけど、別に男から伝えたっていいと思ったから。
それに、僕も理子ちゃんも好きなディズニーの空間で、僕の気持ちを伝えたかったから。
彼女が来るか来ないかもわからないまま、僕は約束の30分前にエントランスに立っていた。
約束の時間が過ぎるか過ぎないかのうっすらと暗くなった頃、遠くから見覚えのある背格好の女性が歩いてくる。
理子ちゃんだ。
僕は、初めて二次会で逢ったあの日、遠くから歩いてきた理子ちゃんの姿をふと思い出した。
「久しぶり。」
変わらぬ笑顔で、でもちょっと緊張したような顔で彼女が口を開いた。
「どうして?どうしてディズニー?」
「どうしても見せたいイベントがあってね。」
「イベント?」
理子ちゃんは、この"バレンタイン・ナイト"を知らなかったようだ。
チケットを見せて、期間限定のイベントだということを伝えると
「えっ?ほんと?楽しみ!!」
緊張気味の顔は、あっという間にいつものはしゃぐ顔に変わった。
イベント会場の「ブロードウェイ・ミュージックシアター」へ向かいながら、変わらぬ彼女の声と嬉しそうな顔が横にある。
ただ、変わってしまったのは、僕と彼女の距離。
一緒に歩いていても、もう昔のように手を繋ぐことはなかった。
会場に入ると、そこはいつものシアターとは違って、"バレンタイン・ナイト"仕様になっている。
バレンタイン当日だったので、カップルだけのベタベタラブラブな雰囲気かと思いきや、家族連れが多かったのに心なしか救われた。
オーケストラの演奏を皮切りに、いろいろなキャラクターが踊ったり歌ったり、時には感動で涙が出そうになるような素晴らしいショーの合間のこと。
舞台スクリーンの大画面に映る文字。
"理子ちゃん、来てくれてありがとう
やっぱり僕は、理子ちゃんを失いたくない
愛してる 結婚しよう 拓朗"
実は僕は、投稿したメッセージがスクリーンに抽選で映し出されるという企画に申し込んでいたのだ。
映し出されるかどうかは、とにかく当日にならないとわからない。
何組のメッセージが紹介されるかすらわからない。
その一か八かに賭けてみたのだ。
この大画面に映る文字を見た理子ちゃんは、すぐに自分のことだと気付き、驚いた顔で僕と画面とを交互に見ていた。
すぐに、また楽しいショーが始まったから、メッセージについて、すぐに会話をすることはなかったけど、僕の想いはこの短い言葉で伝えたつもりだった。
すべてのショーが終わった後、"バレンタイン・ナイト"のチケットを持っていないと食べられないという、オリジナルチョコレート付きのストロベリーパフェを食べながら、彼女はまだ興奮冷めやらぬ感じで、話している。
ただ、あのメッセージに関しては、何も触れようとはしなかった。
もう時間も遅くなるので、僕は本題を切り出した...。
「あのね。なんだかんだいっても、やっぱり僕は理子ちゃんに傍にいて欲しい。だからあのメッセージが僕のすべての気持ちなんだ。返事はこれでいいから。」
そう言って僕は一枚のカードを差し出した。
「何これ?」
「チケットについてきたカードなんだ。このカードにメッセージを書いて投函したら、ホワイトデー前後に届くんだって。これに返事を書いて出してほしい。届くまで、待つから...。」
こんなに短時間で答えを求めるなんて、気が早いかとも思ったけど、短時間でもこれが精いっぱいの気持ちだったから、もう悔いはない。
お互い見えないところで、メッセージカードを書いて、パーク内のメールボックスに投函した。
さすがにここから一人で帰すわけにはいかなかったので、付き合っていた頃のように駅まで理子ちゃんを送る。
ただ...、付き合っていた頃のような会話はなかったけど...。
別れ際、
「またね。」
と言った彼女。
"じゃあね"ではなく"またね"と別れたことに、僕は少しだけ期待をしていいものだろうか。
あの再会から一ヶ月がたち、ホワイトデーが近づくにつれ、僕はポストが気になりはじめた。
13日...、こない。
14日.........、届かない。
そして、15日。
運命のメッセージカードが届いた。
見覚えのあるカード。
震える手で裏を見ると.........。
「ありがとう。
私にも、拓朗君が必要です。
離れてわかったその優しさ。
もう二度と離したくありません。
ミッキーとミニーに負けないくらいの2人でいようね。」
僕たちは、一度は別れてしまったけれど、その期間は2人にとってなくてはならない期間だったように思う。
そのおかげで相手の大切さをわかることができたから。