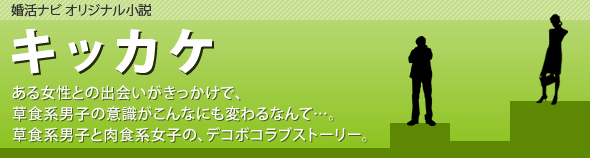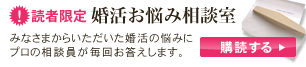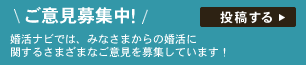約束の時間は、10時。
理子さんを二度目のデートを誘った僕は、一週間前に初めて出逢った理子さんを、今日一日独占するつもりだった。
待ち合わせの駅で、たばこをふかしながら待っていた時のこと。
時間の五分まえに彼女はあらわれた。
「おはようございます。」
「お、おはよ。」
結婚式の時の装いとはまた違い、こないだのプリクラデートの時とはまた違う雰囲気の、ワンピース姿の彼女に、胸の鼓動が高鳴った。
確実に、会うたびに僕の彼女への思いは急上昇しているようだ。
「時間大丈夫かな...。」
理子さんが僕の少し後ろを足早に歩きながら、時計を気にしている。
「大丈夫だよ。もし間に合わなかったら、ひとつ後を見ればいいんだし。」
実は今日のデートは、映画。
定番のデートだが、こないだ話していた時に、お互い見たい映画が同じということが判明。
しかもディズニー映画。
僕はこう見えてもディズニー好きで、最近のディズニー映画も欠かさず見ている。
またタイミングのいいことに、理子さんもディズニーが好きらしい。
そうなりゃ、この映画は2人で行くしかないでしょ!!
「今日は人が多いですねぇ。」
確かに...。
日曜日のディズニー映画ときたら、周りは家族連れや学生、カップルで賑わっている。
もしラブストーリーの映画だったら、上映中も終わった後もストーリーにつられてドキドキ感が得られそうだけど、ディズニーだったら雰囲気なんかありゃしない。
ちょっと映画の選択間違ったかな。
いや、2人とも好きなディズニー映画にして、きっと間違っていなかったのだろう。
なんて、自分に言い聞かしてみる。
「やっぱ映画にはポップコーンだよね!」
と意見が合ったものの、それを買うための行列もすごい...。
「なんだかディズニーランドみたい。」
なんて笑いながら、彼女はこの行列さえも楽しんでくれているようだった。
上映開始が迫っているという人もちらほらいるようで、行列に並んでいる人もなんだか押したり押されたり...。
子供がどこかで泣いていたりと、かなりごったがえしていたその時だった。
後ろの誰かが押したのだろうか。
列全体がぐぐっと前に動くくらい後ろから押されて、僕たち2人も前の人に軽くぶつかってしまった。
将棋倒しにならなかったのが幸いだったが、あまりにごった返していたので、僕は理子さんの手をふと取った。
はぐれないように...。
純粋に僕はこう思った。
このちょっとしたハプニングは、僕に「理子さんと手を繋ぐ」というきっかけを与えてくれた。
僕は何も言わず彼女の顔を見て、ただ微笑んだ。
彼女もとっさの事に驚きながらも、嫌がる様子もなく手を繋いでいてくれた。
「私持つね。」
ポップコーンとジュースのトレーを彼女が受け取ったら、手を繋ぐことができなかったのがちょっとがっかりだったけど、人とぶつかってトレーを落とすことのないように、人ごみを避けながら少し彼女の肩を抱き寄せるように席に誘導した。
席についてからも彼女の方から僕の手を取ってくれて、映画の間中ほとんど手を繋いで過ごした僕たち。
たとえ何かの拍子に手がほどけたとしても、また自然に繋ぎなおす。
この自然なタイミングが僕の心をますます彼女へと引き寄せるのだった。
映画が終わってからも、僕たちの手が離れることはほとんどなかった。
映画館併設のショッピングモールで買い物を楽しんでいる間も、電車で移動する時も...。
きっと周りから見たら、立派なカップルに見えるだろう。
一般的に『草食男子』と呼ばれる僕。
性格的にも、なかなか女性に積極的にはなれないが彼女といるととても楽だ。
それは、彼女が僕を引っ張って行動してくれることが多いから。
「今度はあのお店に入ろう。」
「ちょっとお茶しよっ。」
という具合に。
僕が
(どこに連れて行ったらいいだろう...)
なんて気を遣って考える必要がないのだ。
『グイグイと』という表現まではいかないが、ちょっと僕の手を引っ張り気味に連れて行ってくれる感じ。
実は僕は『私が私が!』的な主導的な女性は苦手なはずだった。
しかし、理子さんはそんな女性と同じようでどこかが違う。
それなりに自分を主張してくるけれど、どこか一歩ひいてくれる。
その間合いが、実に心地よいのだ。
人との波長が合うって、こんなことを指すのかもしれない。
日もすっかり暮れた頃、僕は彼女に聞いた。
「時間まだ大丈夫?」
と。
彼女は実家暮らしだから、きちんと聞いておかなければな...と思っての質問。
「きちんとしてるんですね。」
「えっ?何が?」
と、とぼけたものの、まだ夕食も食べていない時間に時間を気にするなんて...、子供扱いしたと思われたかなと一瞬焦る。
「だって...。私が実家だからでしょ?なかなかそんなことに気付いて聞いてくれる男性っていないですよ。」
「あっ...そう?そんなもんかな。ごめんごめん。気に障った?」
「そんなっ全然!気にしてくれてとっても嬉しい。」
彼女は繋いでいる手をぎゅっと強く握りなおし、僕に笑顔を見せた。
本当は...、本当はここでキスをしたかった。
世の中の男たちは、このタイミングでキスをするかもしれない。
しかし...、僕にはできなかった。
記念になるものだから...、もっといいタイミングまで取っておいたほうがいい、本能からかそう思ったのだ。
こんな僕の行動が、今までの女性たちにとったら嫌だったのかもしれない。
『男らしくない』とか『優しすぎる』とか言われた原因はこれだろう。
しかし、僕はそんな人間だ。
僕は僕の考えで、この恋愛を実らせる。
下手に自分らしくない行動を取って彼女に嘘の自分を見せたくない。
ありのままの僕で勝負するのだ。